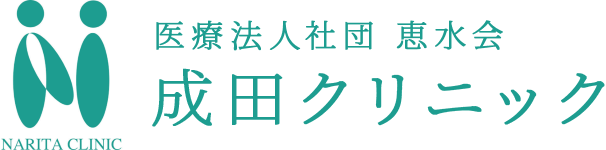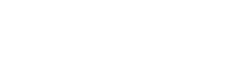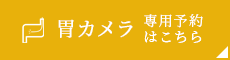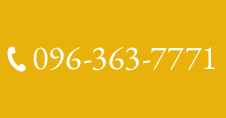コラム
過敏性腸症候群(IBS)だと思っていませんか?
前回は機能性消化管障害の代表疾患である機能性ディスペプシアを取り上げましたので、今回はもう一つの代表疾患である過敏性腸症候群を取り上げようと思います。
過敏性腸症候群は知っている方も多いと思いますし、診断されている方も多いと思います。また、病院受診をしてないくても自分は過敏性腸症候群かもしれないと思っている方もいるかと思います。実際、当院で診断した方の多くは、「そう思ってました」と言われます。また、過敏性腸症候群を疑って受診される方も多くおられます。
題名にもありました「過敏性腸症候群だと思っていませんか?」についてですが、結論から言うと経験上は正解なことが多い印象があります。ただ、違う病気が隠れていることもあり、専門的な診察と検査が必要になりますので、ここで終わらずに最後まで確認をお願いします。
過敏性腸症候群は英語ではirritable bowel syndrome(IBS)と言います。
どういう病気かというと
「お腹の痛みや調子が悪く、それと関連して便秘や下痢などの便通異常(排便回数や便の形状の異常)が数か月続くときに最も考えらえる病気」です。
FDと比べて若干ざっくりした言い回しになっていますが、IBSも大腸に器質的疾患がないことが前提となります。
IBSの診断には国際的な診断基準であるRomaⅣ基準を使用することが多く、IBS定義の参考になると思います。

一応記載しましたが、少しわかりにくいでしょうか。
簡単に言うと、「3か月以上続く腹痛を伴った便通の異常(便秘や下痢)」です。
命にかかわる病気ではありませんが、腹痛やトイレに行くことも多いので、日常生活に支障を来すことがしばしばあります。
IBSはどういう人がなりやすいか
IBSは人口の10%くらいの有病率であり、FDと違って統計的に最近増えていることは無いようです。
IBSのリスク因子としては
・女性
・若年
・心理的問題
・胃腸炎の程度が強い
上記が言われており、年齢が上がるにつれて減少することもわかっています。
IBSの原因
IBSになる原因はわかっていませんが、感染性腸炎後になりやすいことはわかっています。
また、FDと同様にストレスによる脳腸相関が関与しているとされています。

口から入った食物は、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸を通って肛門まで行きます。消化管の蠕動によって食物を運んでいくのですが、食物を感知したり、蠕動の制御のための知覚機能も重要な役割を担っています。運動と知覚は脳腸相関によって制御されていますが、ストレスなどによって不安状態になると、腸の蠕動運動異常によって腹痛が起こりやすくなり、知覚過敏状態となるので腹痛を感じやすくなります。この状態が3か月以上継続している状態がIBSとなります。感染後に起こりやすい原因としては炎症による粘膜の障害や、腸内細菌叢の変化による影響などがあると言われています。
IBSの検査
診断には以下の検査を行います。
大腸カメラ:大腸がん、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)などの器質的疾患の除外
採血・糞便・尿:貧血、炎症、感染、甲状腺機能、糖代謝などの異常の確認
エコー、CT:症状や採血で器質的疾患が否定できないときに行う
ガイドライン上、大腸カメラは弱く推奨とされていますが、発熱、血便、体重減少、異常な身体所見などのアラーム所見(危険徴候)がある場合や、50歳以上の方や、大腸疾患の既往、家族歴がある方は、器質的疾患が隠れていることもありますので、基本的には必須と考えます。
検査で器質的疾患が否定され、前述のRomaⅣ基準を満たすとき、IBSと診断します。
IBSにはブリストル便形状尺度という評価スケールにより4つに分類されます。
・便秘型:タイプ1,2
・下痢型:タイプ6,7
・混合型:タイプ3,4,5
・分類不能型

マイランEPD合同会社発行のアミティーザ患者指導用ツールより引用
IBSの治療
治療としてはストレスがあれば、軽減するようにすることが重要です。その他、食事療法を含む生活習慣の改善や運動療法などが効果があることがわかっていますのでまず行います。
IBSを誘発しやすい食品としては脂質、カフェイン、香辛料を多く含む食品、ミルク、乳製品などがあげられますので控えるようにして下さい。暴飲暴食や夜間の大食は避け、食事バランスに注意し、睡眠・休養をしっかりとりストレスをためないように規則正しい生活をすることが大切です。運動はヨガ、エアロビクス、ウォーキングなどの適度なものでいいとされています。
これで効果がない場合は薬物療法となります。
1.初めに使う薬剤としては、
- 腸の蠕動運動を整える消化管運動改善薬
- 腸の善玉菌である乳酸菌、ビフィズス菌や酪酸菌などのプロバイオティクス
- 腸内の水分量を調整する高分子重合体
などがあり下痢型・便秘型どちらにも使えます。
2.次に使う薬剤は
下痢型:腸の運動異常や知覚過敏を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬や下痢止めであるオピオイド受容体作用薬
便秘型:便を柔らかくする粘膜上皮機能変容薬、下剤
その他、腹痛に対しては抗コリン薬、不安が強い場合は抗不安薬や抗うつ薬を使用し、漢方薬や抗アレルギー薬を使用する場合もあります。
また、ガイドラインで鍼灸も効果があると述べられておりますので、試してみるのもいいかもしれません。
前述したようにIBSは年齢とともに軽快し、50歳以上ではそれより若年の方より発症しにくいとされていますが、病型が変化することもあります。(下痢型⇄便秘型)
また、FDや胃食道逆流症と合併しやすく、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患になりやすいと報告がありますので、定期的に診察や検査を行うことも必要です。
IBSにはストレスが関与しており、不安が強いことも要因となります。病型も4種類ありFDと同様にその患者様にあった治療法を見つけていく必要があります。そのためには医師と患者様との信頼関係が大事ですので、何かりましたら当院へご相談ください。
成田クリニックでは胃腸科・消化器外来を行っており、下痢・便秘などの症状に対応しています。IBSの診断には大腸カメラが必要になりますので、お気軽にご相談下さい。
機能性消化管障害については「ブログ:機能性消化管障害」をご覧ください
機能性ディスペプシアいついては「ブログ:機能性ディスペプシアは意外と多いんです」をご覧ください