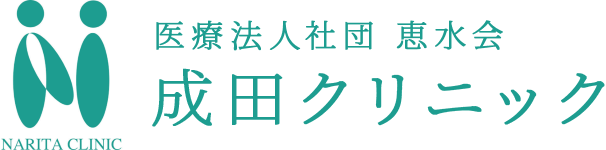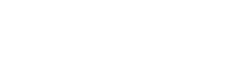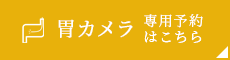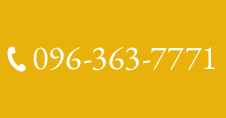コラム
その症状は逆流性食道炎かもしれません!
【概要】
逆流性食道炎は消化器疾患の中では一般の方でも知っている方が多い疾患ではないでしょうか。医学的には胃食道逆流症(GERD:gastroesophageal reflux disease)と言いますが、一般的には逆流性食道炎の方がよく使われてます。GERDは近年増加傾向であり、マスコミで取り上げられたり、健康診断の胃カメラで指摘される方も多く関心が高まっているのではないでしょうか。以上のことからGERDについて詳しく解説していきたいと思います。
定義ですが
「胃内容物の逆流によって引き起こされる症状や合併症を引き起こした状態」
となっております。言ってることは何となくわかりますが、何のことかはわかりにくいかと思います。
典型的な症状は胸やけと呑酸です。胸やけはみぞおちの上くらいが焼けるように熱くなったりジンジンしたり締め付けられる症状で、呑酸は苦くて酸っぱい液体が上がってくる感じです。その他、胸痛や咳の原因になることもあり、心疾患や呼吸器疾患との鑑別が必要になる場合があります。

GERDには、胃カメラで①食道がただれている(粘膜障害がある)びらん性GERDと②食道にただれがない非びらん性GERD(NERD)に分類されます。
| ①びらん性GERD(逆流性食道炎) | ②非びらん性GERD(NERD) | |
| 粘膜障害 | あり | なし |
| 自覚症状 | 有無は問わない | あり |
GERDは欧米に比べ日本での有病率は低いと考えられていましたが、近年の食生活の欧米化(脂ものが増えた)、ピロリ菌感染の低下(元気な胃の人が多くなった=胃酸の分泌が活発な人が増えた)、GERDの認知度の向上などにより、日本におけるGERDの有病率は増加傾向であり、だいたい全人口の10~15%と言われています。
GERDは割と自覚症状が強く、食事や睡眠に支障を来すこともあり、生活の質(QOL)を低下させる原因となっています。一度罹患したことがある方や、GERDの知識がない方は、かなりの不安に駆られることが多く、がんなどの大きな病気があるのではないかと心配で受診する方もおられます。実際は早期の胃がん・食道がんであれば症状を来すことは稀であり、進行がんにならなければ症状がでないことが多いですが、鑑別のためには胃カメラ検査をすることが必要となります。GERDであれば内服治療が効果的ですので、まずは病院を受診してもらい早期に診断治療を行うことが重要と考えます。
【GERDの原因は?】
主な原因は胃内容物による過剰な食道内の曝露です。通常は食道と胃のつなぎ目が逆流を防ぐようになっており、逆流しても食道と胃の動きで胃に押しやってくれます(蠕動)。GERDは食道と胃のつなぎ目に障害があるときに起こりやすいです。
・胃酸が多い
ピロリ菌感染があると胃酸分泌が減りますが、除菌を行うと胃酸分泌が改善してきます。近年ピロリ菌感染者が減っていることと、除菌を行った人が増えていることが要因です。
・食道・胃の蠕動が悪くなっている
強皮症や糖尿病などがある方は消化管運動機能が低下しており、蠕動が悪くなる。
・食道・胃のつなぎ目が緩くなっている
過食・高脂肪食、加齢、薬剤(カルシウム拮抗薬や亜硝酸薬など)が誘因となり、食道の筋肉の機能が悪くなることによってつなぎ目が緩くなる。食道裂孔ヘルニアや胃術後なども要因となる。

食道裂孔ヘルニア
胃が横隔膜より上に入り込むことによってつなぎ目が緩くなる病気
・お腹の圧が高くなっている
肥満・妊娠中の方・前屈位の方は腹圧が上昇することにより逆流しやすくなる
その他、ストレスや睡眠不足による食道知覚過敏が誘因となりますが(特にNERD)、ここは以前投稿した機能性ディスペプシアに関連しますので興味のある方はこちらから。
【どうすれば診断できる?】
胸やけ、呑酸などの自覚症状から推測することが可能ですが、内視鏡検査(胃カメラ)を行うことで診断できます。食道のただれ具合で分類されており、ロサンゼルス分類と言います。ただれ具合がひどければ自覚症状が強いことが多いですが、ただれ具合の重症度が必ずしも自覚症状に比例するわけではないので注意が必要です。自覚症状と食道に粘膜のただれがあると間違いなくGREDとなりますが、健康診断の胃カメラで食道の粘膜のただれがたまたま見つかることもありますし、食道のただれがないのに症状がある方もおられます。「GRED Q」などの専用の問診票があり、診断に有用とされています。内視鏡検査は必ずしも必要ではないとされますが、がんや胃潰瘍などの病気が隠れていることがありますので、今まで検査をしたことない方や1年以上行っていない方は検査をすることをお勧めしています。その他、24時間pHモニタリングという検査がありますが、胃管を24時間入れる検査なので苦痛をともなうことと、できる施設が限られているのであまり行われておりません。


【胃カメラによる分類(ロサンゼルス分類)】
| Grade N | Grade M | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
| 内視鏡的に 変化を認めないもの | 粘膜障害は 認めないが、色調変化を認めるもの | 5mm以下の 粘膜障害 | 5mmを超える粘膜障害 | 2条以上の粘膜ひだにまたがる粘膜障害 | 全周の75%を超える 粘膜障害 |






【治療はどうする?】
プロトンポンプ阻害薬(PPI)、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(PCAB)などの胃酸を抑える薬が第一選択薬となります。その他、酸を中和する薬や粘膜を保護する薬、消化管の動きを改善する薬や漢方薬も使用されます。
・胃酸の分泌を抑える薬:PPI、PCAB、H2-blockerがあります。通常ではPPIかPCAB、重症ではPCABを使用することが多いです。
・胃酸を中和したり、粘膜を保護する薬:制酸薬やアルギン酸塩などを使用します。補助的な使われ方が多いです。
・消化管の動きを改善する薬:モサプリドやアコチアミドを使用します。PPIとの併用で使用することが多いです。
・漢方薬:六君子湯を使用します。PPIとの併用で使用することが多いです。
ほとんどの方が内服治療で改善しますが、薬をやめると再発する方もいます。薬が効果がない方は手術になることもあり、逆流を防ぐための手術や食道裂孔ヘルニアがあればそれに対しての手術を行います。
【普段から気を付けることは?】
GREDは日常の動作・生活や食事に関係しており、それらを守らないと症状が悪化したり再燃しやすくなります。
生活面:腹部の締め付け、前屈位、右を下にして寝る、肥満、喫煙など
食事面:食べ過ぎ、就寝前に食事する、高脂肪食、甘い物、チョコレート、コーヒー、柑橘類、炭酸飲料、アルコール



上記をしないことで症状を抑えることができたり、再発しにくくなります。
また、体重を減らす、頭を高くして寝る、食後すぐに横にならないなどのことをすると効果があると言われています。
【合併症はありますか?】
食道のただれが続いたり、ひどくなると出血し、吐血することがあります。また、繰り返すことで食道が狭くなったり(狭窄)、バレット食道という状態になればがんができやすくなったりします。
慢性的に咳が出るようになったり、ぜんそく、のどのポリープができやすくなったりします。慢性的に咳が続く方はGERDによる症状のこともありますので、ときどき呼吸器内科から胃カメラの依頼があったりします。
全身性硬化症(強皮症)などの膠原病やその他の疾患が背景にあることもあります。
【その他】
胸やけ、呑酸の症状やそれに似たような症状は他の疾患の可能性もあります。
消化器疾患:好酸球性食道炎、食道がん、胃潰瘍、胃がん、胆のう炎、総胆管結石、膵炎など
その他の領域の疾患:ぜんそく、気管支炎、肺炎、狭心症、心筋梗塞、肋間神経痛など
内視鏡で食道のただれが無かったり、内服治療が効果がないときには上記疾患の可能性もありますので追加の検査が必要なことがあります。
GERDは消化器内科ではごくありふれた疾患であり、一般の方にも浸透しつつありますので解説させていただきました。GERDは日常生活に支障を来すほどの症状がありますが、内服治療で改善が見込める疾患です。一度治っても生活習慣や食事、ストレスによって再発することがありますので注意が必要です。また、違う疾患が隠れている場合もありますので、きちんと診断することが重要であり、症状がある方は内視鏡検査をお勧めしています。
当院では経験豊富な内視鏡専門医による胃腸科・消化器外来と内視鏡検査(胃カメラ)を行っています。鎮静剤を使用した検査を行っており、苦痛の少ない検査を心掛けております。予約から検査後までの流れを説明していますのでご参照ください。